佑斗の朝は、大船駅西口の喧騒とは裏腹に静かに始まる。午前11時、いつものようにトースト一枚とインスタントコーヒーで済ませた後、彼は職場である古本屋「読処 たもつ」へ向かう。
「ここに並ぶ本たちって、売れるために書かれたんじゃなくて、残るために書かれてるんですよね」
古賀佑斗、28歳。夢見たのは作家。だけど現実は、人生の脇役を演じているような毎日だ。
都内の大学に進学した彼は、文学に心酔した。卒業後、小さな出版社で編集見習いを経験したが、次第に社会の波に押しつぶされていく。社員にはなれず、原稿も採用されず、同棲していた恋人にも見捨てられた。
「書く意味って、あるのかなって思っちゃったんですよ」
彼は大船に逃げるように戻り、今の古本屋で働き始めた。住んでいるのは駅から徒歩15分、線路沿いの築40年の木造アパート。夜、カーテンの隙間から通過する電車の灯りを眺めながら、缶チューハイを片手に中上健次を読みふけるのが唯一の楽しみ。
元カノのインスタはまだフォローしたままだ。たまに投稿される“幸せそうな”日常に胸を締めつけられながらも、なぜか「いいね」を押せない。
「俺、まだ終わってないよな…」
そうつぶやいて閉じたノートには、1ページ分の短編が綴られている。いつか、誰かの心に届く日を信じて。
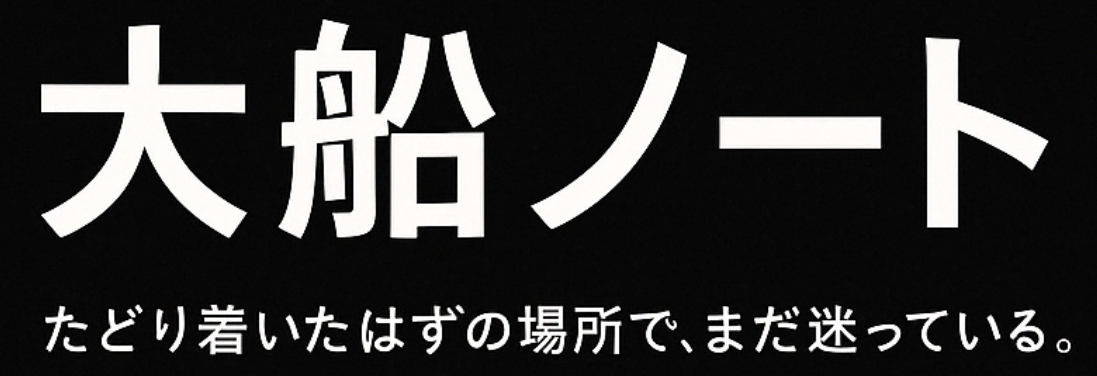



コメント